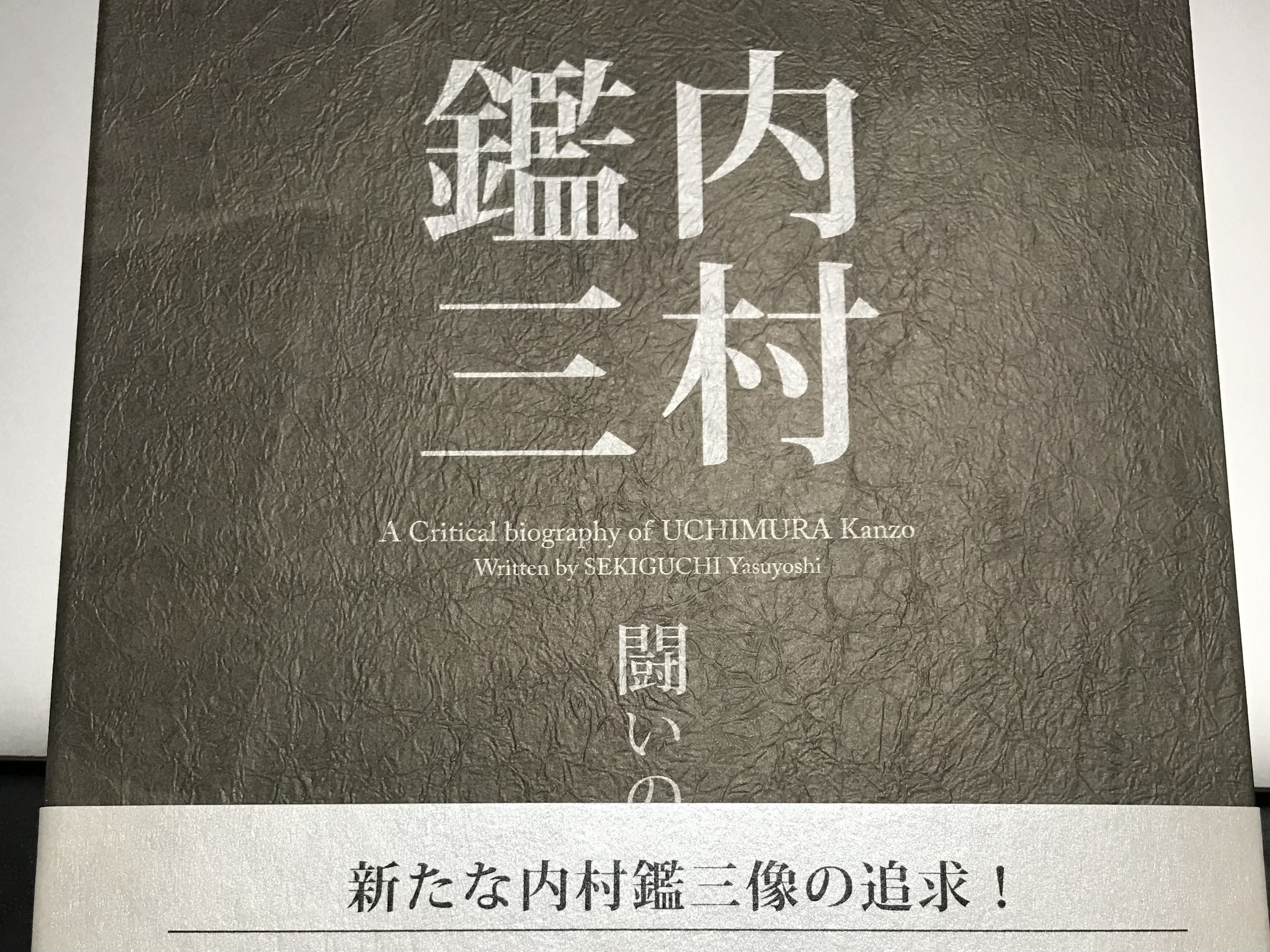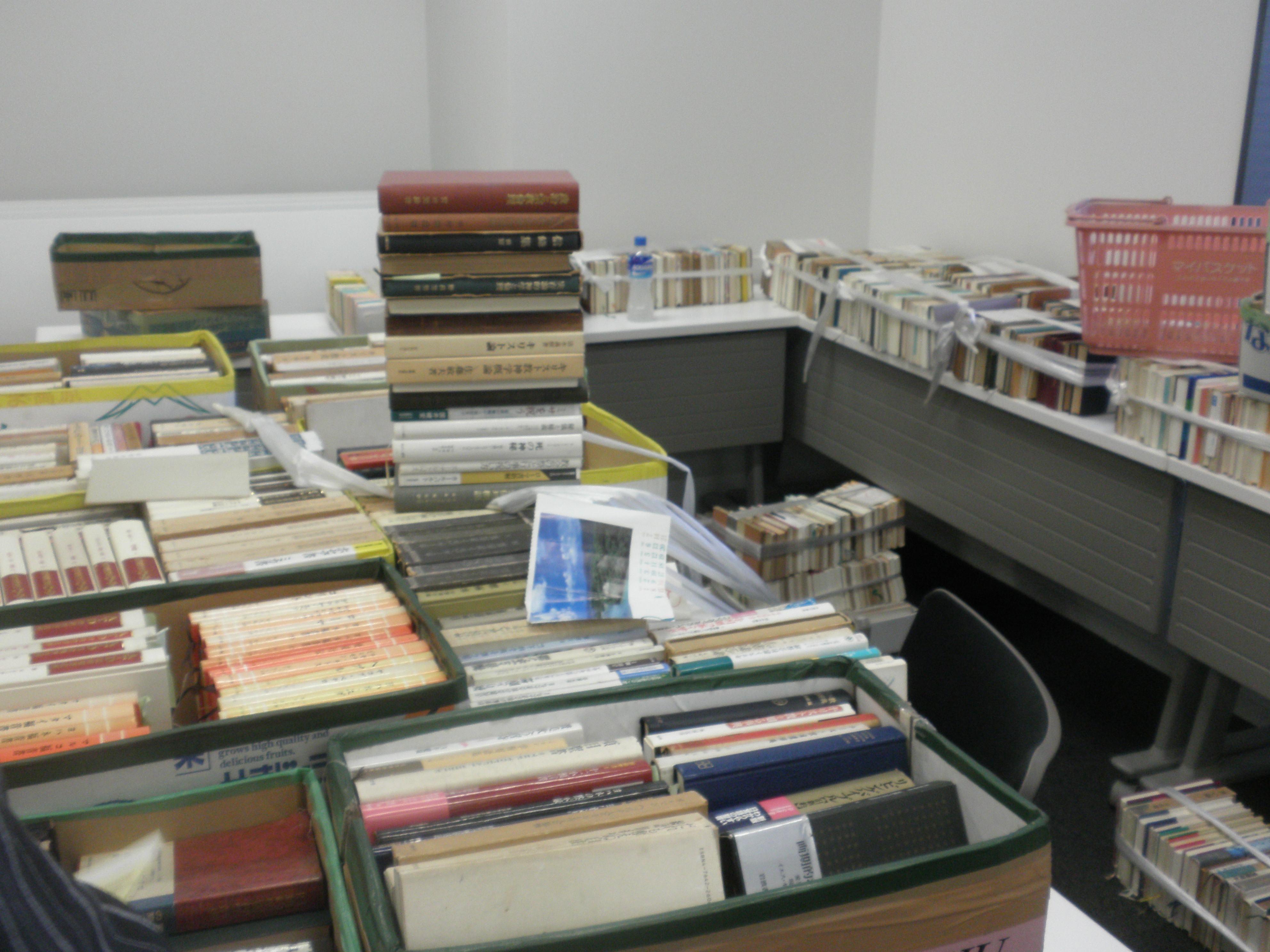・聖書通読(朝の素読 -聖書編-)
2021年4月1日から、聖書を毎日1章ずつ読んでいます。ツイキャスを利用して、朝7時〜を基調に、30分以内の配信となります。
・日曜礼拝(2015年以降の礼拝・ミサ出席の記録)
2015年3月から、教派を問わず、各地の教会をめぐってきました。その記録です。現在は、篠崎キリスト教会(日本バプテスト連盟)と、聖イグナチオ教会(カトリック・イエズス会)の朝夕の礼拝・ミサに参加しています。
・研究書庫「聖書の実体・体系・構造」(フリー共有データ)
2023年7月から、上記の聖書通読、礼拝・ミサの記録として、聖書のデータベースの作成を始めました。2030年までには、使える情報が集約されることでしょう。ノアの方舟の完成を待ち望むような感覚で、ゆっくりお待ちください。
〈参考資料〉
◇創世記からの参考資料:イエス・キリストの系図
(アダム・エヴァ以降のすべて)
◇出エジプト記以降の参考資料:世界史の窓「エジプト」
◇列王記以降の参考資料:ソロモン王死後の、分裂イスラエルの南北王の系譜
◇列王記以降の参考資料:世界史の窓「アッシリア」
◇エズラ記・ネヘミヤ記の参考資料:世界史の窓「アケメネス朝ペルシア」
キリスト教精神文化研究室は、いずれの組織・団体にも属していない、独立系の個人研究室です。無教会主義の立場ですが、使徒信条に基づく聖なる普遍の教会を信じます。
◇共同代表(倉井)の主張:ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の著者はプリスカである
CRUISE RECORD 2010-2030
ブリンディジをめぐるあれこれ
2024年6月、イタリアで、G7プーリア・サミットが開催された。欧米各国、日本、さらに世界各地から招待された国家および国際機関のトップが集まり、地球環境や今後の国際開発、安全保障などの議題について話し合った。
プーリアという地名を聞いてすぐに場所が思い浮かぶ人は、まあまあの地理好きか、あるいは旅行マニアかもしれない。イタリアの国土を長靴にたとえるなら、かかとの部分にプーリアはある。古代アッピア街道の終点ブリンディジを擁し、そこからギリシアをはじめとする各地に船が出ていた。古くから海上交通の要衝であり、ブリンディジは第二次世界大戦の末期にイタリアの臨時首都が置かれた時期もあるから、歴史的に意味ある場所で重要なサミットが開かれたと言えるだろう。
文化的な話題に触れておくと、森鷗外の小説『舞姫』は、ブリンディジ港から日本への帰路についた主人公がサイゴンで書いた手記という設定である。作者鷗外もヨーロッパ旅行の経験があり、それをもとに書かれたと言われる。ただし、実際に鷗外が利用したのは、フランスのマルセイユ港である。鷗外自身がイタリアを訪れたという記録はない。つまり、『舞姫』のストーリーの出発点にイタリアのブリンディジが設定されているのは、小説のオリジナルの要素と言える。
ここからは、ちょっとしたトリビア。森鷗外の時代、ブリンディジを出発した船舶は、サイゴンを経由しなかった。つまり、ブリンディジ~サイゴン~日本(横浜?)をむすぶ船は、小説『舞姫』の中にしか存在しなかったことになる。作者自身はマルセイユ発、サイゴン経由で日本に戻ったから、そのつもりで書き間違えた、とも言えるし、むしろ、小説独自の展開として解釈することもできる。主人公は、イタリアでどんな旧蹟を見て、帰りの船内で何を考えたのだろうか。(2025年5月30日執筆、7月28日確定)
AIでスポーツは面白くなるか 〜みはるかす神戸のブルーウェーブ〜
2025年のプロ野球。オリックス・バファローズは、岸田護監督の一年目のシーズンを迎えた。前年は6チーム中5位。新たに就任した岸田新体制は、オープン戦こそ苦戦したものの、公式戦では単独首位をひた走り、6月のセ・パ交流戦の前までに2位でフィニッシュした。また、今年は1995年の阪神・淡路大震災から30年。オリックスの拠点、神戸で開催される試合では、選手たちが30年前のなつかしい青色のユニフォームをまとい、あの頃の応援歌が空に響いた。当時ヒーロー選手だったイチローからも、激励のメッセージが届けられた。ファンにとっては、記憶に刻みつけられる一年になることがすでに決定づけられていると言ってよい。
セ・パ交流戦の前、5月31日に神戸で開催された試合は、オリックスが西武に勝利。だが、翌日は西武に9回で勝ち越された。守護神マチャドの外角低めのスライダー(変化球)はボール判定。西武のバッター外崎のハーフスイングも認められなかった。試合後、SNSを見ると、「今回は審判VSオリックスVS西武だったな……」というファンのぼやきがいくつも流れていた。試合に負けた悔しさからか、「もうスポーツの審判はAIにしようよ」なんて提案も見られた。
でも、投手マチャドは、結果を潔く受け入れていたようだった。きわどい判定も、試合の面白さの一つのはずだ。もし、すべての判定をAIに任せたら、たしかに正確かもしれない。ただ、スポーツには経験に基づく判定が必要な場面もあるだろうし、機械に任せて試合をすることが緊張感あるプレーにつながるとは思えない。
とにかく、試合が終われば“ノーサイド”(ラグビー用語だが、すべてのスポーツにこの精神が大切だ)。勝者西武を讃えようじゃないか。──神戸に来てくれてありがとうな。人と人が真正面からぶつかるんが最高におもろいねん!(2025年6月2日)
街にも顔がある
街にも顔がある。──これは比喩でもあり、言葉通りの意味でもある。
10年前から、東京都江戸川区のS町にある教会に通っていた。そのS町を、先日、初めて散策した。地下鉄の駅から教会までは、どの経路で行っても、すこし距離がある。バスに乗りなれない僕は、いつも道に迷い、バスを乗り間違え、あげく、長い距離をとぼとぼ歩いて通ったものだ。先日は少し時間があったから、午前中に用事を済ませた後、あらためて街の中を歩き回ってみた。
街の中には、昔からの石塔(庚申塔)や地蔵尊が立っている。人々の信仰心の現れ、ということでもあるかもしれないが、江戸時代からの街道沿いということを考えれば、それらは道案内のしるし、といったほうがよいのかもしれない。それにしても、この石塔は、──僕は思った。なんで、道順に背を向けて立っているのだろう?
その謎を解くために、帰宅後、地図を入念に見詰めてみた。そして、「あっ!」と思わず声が出た。
自分が思っていたS町の見取り図が、実際と逆だったのである。
地下鉄の駅から教会へ向かうときは、徒歩にせよ、バスにせよ、町の西側から向かうことになる。僕はこれまで10年間、「西側が、街の正面」だと思っていた。
しかし、それは間違いだったのだ。
江戸時代、まだS町が村だった頃は、東側の江戸川を利用する水運が盛んだった。人々は、船で物資を運んだ。また、徒歩でS村に入る人々は、江戸川沿いの街道を利用した。つまり、本来のS町の入口は、東側なのである。地下鉄の開通は1980年代後半だから、S町の歴史から言えば、ずっと後のことなのだ。
「東側が、街の正面」だと思って眺めてみると、風景の見え方ががらっと変わる。あの石塔は、江戸時代の村の中心地に立っていて、まさしく街道の入口側を向いて立っている。石塔の指示する方向に歩けば、歴史的建造物がたくさんある。これまでは、地図を逆さに見ていたようなものだ。僕の認識が、ずっとあべこべだったのだ。(2025年4月18日執筆、5月27日確定)
まず仮説を立てる 〜プリスカとアキラの秘密〜
小説を書くとき、読者に提示すべきメッセージや、背景となる世界観をどのように構築すればよいか? ──昨年から執筆を開始した僕の小説は、今後数十年書きつづける壮大なシリーズとなる予定だ。だから、一作ごとのテーマ設定はもちろん、シリーズ全体を貫く世界観、長い時間をかけて読者に問いかけるべきメッセージがなくてはならない。
多くの先輩作家たちは、このようなとき、古典、正典(カノン)に価値を見出してきた。キリスト教、仏教、あるいは、世界各地の民族神話。人々に長いあいだ読み継がれ、しかも、いまだ読むべき余地が残っているテクストを典拠として、新しいストーリーを創造する。正史に対して別視点から解釈を加える、あるいは、SFならば並行世界を描くことも可能だ。数千年読まれてきた正典をもとにすれば、数十年書きつづけても源泉は涸れまい。
僕の小説シリーズは、「新約聖書の中で唯一、著者が誰なのかがまったく不明の文書」(ヘブライ人への手紙)に焦点を当てる。すなわち、主人公三人組の一人であり、初代教会の女性奉仕者である*プリスカを著者候補とする。彼女の具体的な人物像については正典に詳述されていないが、僕の小説では、「ユダヤの青年に恋したローマ政府高官の娘」「困難を乗り越えて結ばれた二人の愛が、皇帝ネロの支配体制を根本から揺るがせる」という、大胆な仮説を立てた。この仮説に近い見解は、実際に聖書学の議論として存在する。だが、考古学的な新発見がない限り、論証することは困難だろう。
小説というジャンルの自由なところは、「もしも、彼女が著者だったら?」という仮説の下で、2000年前の女性たちの活躍をありありと描くことが許されていることだ。研究論文を書くなら、仮説を論証する厳正な手続きが必須である。でも、創作はそうではない。典拠に拠りつつ、書き手の想像力を最大限にはばたかせて、現代の読者たちに新しい価値観を示すことができる。(2025年4月17日執筆、5月27日確定)
- *プリスカ:プリスキラとも。夫であるユダヤ人アキラとともに、帝政期ローマの各地に拠点をつくり、人々の生活と活動を支援した
「マグダラのマリア再考」
西洋絵画の主要なテーマの一つが、宗教画である。教会建築や音楽と並んで、伝統的な宗教をモチーフとする絵画は、世界中の人々を魅了してきた。
さて、その西洋の宗教画の中でも、多くの人々が好むモチーフの一つとして、マグダラのマリアという女性について取り上げてみたい。イエスの母マリアではなく、イエスの弟子の一人とされている女性である。西洋絵画史の中で、マグダラのマリアは、自らの罪を悔い改めた女性として描かれてきた。過去、多くの画家たちが、どこか妖しい魅力のある彼女を絵画のモチーフにしてきた。また、その影響は、西洋の絵画だけにとどまらない。近代日本の小説の中でも、泉鏡花の『高野聖』や、夏目漱石の『三四郎』、谷崎潤一郎の『痴人の愛』などに登場する妖(あや)かし(=魔性)の女、つまり、主人公の男性を翻弄する女性たちの原的なモチーフとして位置づけられてきた。
ところが近年、このようなマグダラのマリアをめぐる通説に、異論が提示されている。彼女は、二千年前の宗教共同体を率いた女性リーダーの一人だったのではないか? 通説では、彼女の役割が過小評価されてきたのではないか? というのである。たしかに、イエスが危機に直面したとき、ほかの弟子たちは恐れをなして逃げだしたのに、マグダラのマリアは逃げなかった。近年は、そんな彼女を主役とする映画も制作されている。男性目線で描かれる謎めいた女性というモチーフから、女性自身を主体化するストーリーへの転換である。これは、伝統的な絵画や小説の分野に限らず、ジェンダー平等をめざす現代の社会的要請にも応える、新しいマグダラのマリア像と言えるかもしれない。(2024年11月27日)
ニチアサの目覚め 〜『ひろがるスカイ!プリキュア』〜
日曜日の朝に、子供向けのテレビ番組が放送されている。子供たちだけでなく、アニメや特撮が大好きな大人たちも楽しんでいる。
「ひろがるスカイ!プリキュア」は、シリーズ20周年を記念するアニメ作品である。記念作にして異色作とも言われている本作では、これまでのシリーズのさまざまな“お約束”が破られている。どこにでもありそうな街に住んでいる普通の女の子が変身して、悪と戦う……というのが、過去の作品の“お約束”だった。一方、今回の主人公は、空の上の異世界からやってきた。初登場時から、強い。変身していない普通の状態でも、岩を素手で割ることができる。さらに、山の中で修業をしたり、滝に打たれたり、河原で決闘したりする。どう見ても、普通の女の子ではない。まるで、昭和のスポ根漫画のようである。放送開始当初から、「歴代キャラの中で最強なのでは?!」と、ファンのあいだでささやかれていた。
だが、この作品のストーリーの中では、じつは、強さだけが決定的な要素というわけではない。圧倒的な強さで敵をねじ伏せるだけなら、ヒーローとは言えない。主人公が変身して敵と戦うことになったきっかけは、「相手がどんなに強くても正しいことを最後までやり抜く」という覚悟だった。何のひねりもない、正しさの全面的な肯定が、ストーリーの軸になっている。
さらに、ここでいう正しさは、主人公の独りよがりな信念ではない。自分勝手な敵のことは許さないが、敵が窮地に陥っていたら助ける。敵を倒すのではなく、浄化して、本来あるべき姿に戻す。さまざまな経験の中で自分自身の未熟さを自覚しても、仲間を信じて、立ち止まらずに前に進む。公正な世界への信頼や、他者との協調が、主人公たちの成長を支えている。
現代の社会では、大人になるにつれて、直球の正しさを信じられなくなりがちだ。みんな、「けっきょく、正しいことばかりじゃない」とか言って、世の中に染まっていく。だが、世界の公正性を信じ、ストレートに他者のために行動する姿勢は、やはり、失われるべきではない。(2023年11月30日執筆、2024年1月29日確定)
関口安義『内村鑑三 闘いの軌跡』新教出版社
これは、内村鑑三と無教会キリスト教の研究において重要な一冊です。
内村をめぐる既存の言説は、研究というより、顕彰でした。その理由は明白です。彼は信仰者であり、キリスト教伝道者であり、そして、彼について書籍や論文を書いている多くの人々もまた、信仰者であり、彼の後継者だからでしょう。著者の関口安義氏は、文学研究の実証的・客観的アプローチによって、内村研究に内側から楔を打ち込んだと言えます。
個人的な回想を記しておきます。関口安義氏の芥川龍之介に関する著作は、高校時代から愛読していました。中学三年生の夏、芥川の「トロッコ」を読んだときの“文学的衝撃”とも呼べる体験から、10代後半の時間の多くを文学のために費やしてきました。それは、或いは空費と云っても好いかもしれません。学校の授業の予習を放棄して(!)、日ごとに、夜ごとに、岩波新書を読み耽ったものです。関口先生の著書の記述をたよりに、高校の柔道の時間に、芥川と同じ中堅にしてもらったこともありました(結果は、中堅にて一本負けで、芥川のように「一人破る」とはいきませんでした)。そして、関口氏と同じように、文学の道から、無教会キリスト教に傾斜し、大学と大学院、さらに、その後の道行を歩んできました。
翻って現在。無教会第五世代の一人として、エクレシアの継承には完全に失望しています。そのことについては、また詳しく書くことにします。ただ、か細い信仰共同体がいままさに消えようとする最後の瞬間に、文学研究者の冷徹な目が入ったことを希望とすべきでしょう。(2023年9月30日)
復活書店の山口さんのこと
出版業界のことを眺めていると、どうしても思い出してしまうことがある。今から5年以上前、ある古書販売店の人と出会った時のことだ。
その古書店の店主の名は山口さんという。人文書を中心に数千冊を集め、各地のイベントで古書のバザーを開いていた。山口さんは一部の業界では有名で、お名前はずいぶん前からよく知っていた。それで、ある公共施設の蔵書を引き取ってもらう時に、山口さんに来てもらった。その時に、出版業界の裏側の話を伺った。
それは、電子書籍ブームが始まって5年ほど経過した頃だった。紙の本、特に文学全集の価格が信じられないほど下がっていること、それゆえ古書を売っても経費ばかりかさむことを山口さんは率直に話してくれた。それでも全国各地で古書バザーを開くのは、「長年付き合いがある人たちに会いに行くため」だそうだ。「本当は趣味の魚釣りをするお金を稼ぎたくて始めたのに、儲けはほとんどない」と苦笑する山口さんの顔が印象的だった。
その後、付き合いができて、山口さんのお手伝いで名古屋のイベントに行った。山のような古本をビニールひもで縛り、トラックに積んで、バザーの会場で荷解きをする。駐車場と会場の間を何度も往復し、少しずつ台車で運んで、棚に並べる。バザーが終わったら、もう一度古書をビニールひもで縛り、トラックに積む。山のような本が飛ぶように売れればいいが、現実は厳しい。しかし、それでもやる。
電子書籍の販売なら、こんな苦労はない。データをダウンロードして終わりだ。傍から見れば、日本各地で紙の本を売って回るなど、徒労だと思われるかもしれない。でも、数年たった今でも、僕はこの時の体験をはっきり覚えている。売れ残った古本をトラックに積んでくたくたになった東京への帰り道、深夜の高速道路で、オリオン座に向かって走った時の光景を忘れることはできない。
時代の流れが速くなり、情報のやりとりも速くなった。しかし、本当に大切なものは、自分の身体を通して体験した出来事の中にこそあるのではないか。(2022年、日付不詳)