ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の著者はプリスカである。
大祭司イエスへの信仰。それは、プリスカとアキラの家の教会の指針であった。……という仮説。
ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の著者には、パウロ説(学術的には少数意見?)、ルカ、バルナバ、シラス説、アポロ説(マルティン・ルターが支持)の他に、プリスカが書いたという説が存在する。(ただし前提として、2世紀には著者不明となっており、各論の論証は困難。)
関根正雄・木下順治(編)『世界古典文学全集第5巻 聖書』筑摩書房の解説は、「ヘブライ人への手紙」の著者問題に関して、プリスカ説を紹介している(新約の担当は木下)。最初、神学者ハルナックがプリスカ説を主張した。木下は上記の編著解説では控えめに紹介しているにとどまるが、単著ではプリスカ説を強く主張している、らしい(※註:2024年11月14日時点では未確認)。
その他、いくつかの註解書で、プリスカ説に言及している。海外の研究に目を向けると、福音派のフェミニズム団体、CBEインターナショナルの代表ミミ・ハダドが、この説を強く主張し、団体としてもそれを支持する傾向にある。
無教会の聖書学者・伝道者で言えば、黒崎幸吉もこの説を取り上げている。一方、塚本虎二は、プリスカ説に言及しつつも、想像力の産物にすぎないと否定的である。
(総論)
イクトゥス・プロジェクトは、神学・信仰的には中立でありたいと考えています。ただし、共同代表の個人の見解としては、ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の著者=プリスカ説にこだわり、生涯を賭けて論証してゆきたいと考えています。
ヘブライ人への手紙(ヘブル書)抄
「神は、かつて預言者たちによって、多くのかたちで、また多くのしかたで先祖に語られたが、この終わりの時代には、御子によってわたしたちに語られました。」「御子は、天使たちより優れた者となられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。」(1章1-2, 4節)
「それで、イエスは、神の御前において憐れみ深い、忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。」 (2章17節)
「だから、天の召しにあずかっている聖なる兄弟たち、わたしたちが公に言い表している使者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。」 (3章1節)
「この大祭司は、わたしたちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われたのです。」 (4章15節)
「キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして、完全な者となられたので、御自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。」 (5章8-10節)
「わたしたちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる、安定した錨のようなものであり、また、至聖所の垂れ幕の内側に入って行くものなのです。」 (6章19節)
「このように聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、わたしたちにとって必要な方なのです。」「このいけにえはただ一度、御自身を献げることによって、成し遂げられたからです。」 (7章26・27節)
「今述べていることの要点は、わたしたちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座に着き、人間ではなく主がお建てになった聖所また真の幕屋で、仕えておられるということです。」 (8章1-2節)
「こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは、最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちが、既に約束されている永遠の財産を受け継ぐためにほかなりません。」 (9章15章)
「いったい、律法には、やがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。」「しかしキリストは、罪のために唯一のいけにえを献げて、永遠に神の右の座に着き、その後は、敵どもが御自分の足台となってしまうまで、待ち続けておられるのです。」 (10章1・12節)
「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。(中略) 信仰によって、わたしたちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは、目に見えているものからできたのではないことが分かるのです。」 (11章1, 3節)
「すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして、だれも主を見ることはできません。」「このように、わたしたちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。」(12章14, 28節)
「金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。」「イタリア出身の人たちが、あなたがたによろしくと言っています。恵みがあなたがた一同と共にあるように。」(13章5, 24-25節)
※新共同訳より引用
2021年から聖書通読をはじめて、「マグダラのマリアに対するイメージが一変した」「ずっと苦手だったヨハネ伝が魂をゆさぶってきた」「(著者プリスカ説を通じて)ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の研究に生涯を捧げることが決まった」といった、良い変化がありました。進むべき方向が定まった、と言えます。
ある一人の人間がいのちを賭けて取り組むべきテーマは、第三者から見れば、荒唐無稽に思えるかもしれません。しかし、たとえ、一見エクセントリックな主張に思えたとしても、自分自身の信仰の根幹にかかわることですから、主張しないわけにいきません。
──「なぜ、ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の著者=プリスカ説にこだわるのか?」
答え:それが、人生を賭ける情熱の源泉だからです。今後、生涯のすべてをこの説に献げます。もちろん、容易に論証可能とは考えていません。考古学的な新発見がない限り、ヘブル書の著者は不明です。それでも、彼女の声を聞いた。だから信じる。
(根拠なき宣言)
ヘブライ人への手紙(ヘブル書)の著者=プリスカ説は、(「悪魔の証明」に対置される)「天使の証明」です。 真面目なユダヤ人青年に恋したローマ人の娘が、日夜、聖書を読み耽り、信仰に導かれた。彼女たちの愛がなければ、キリスト教会の歴史は始まらなかった。二人の愛こそ、人類の希望なのです。
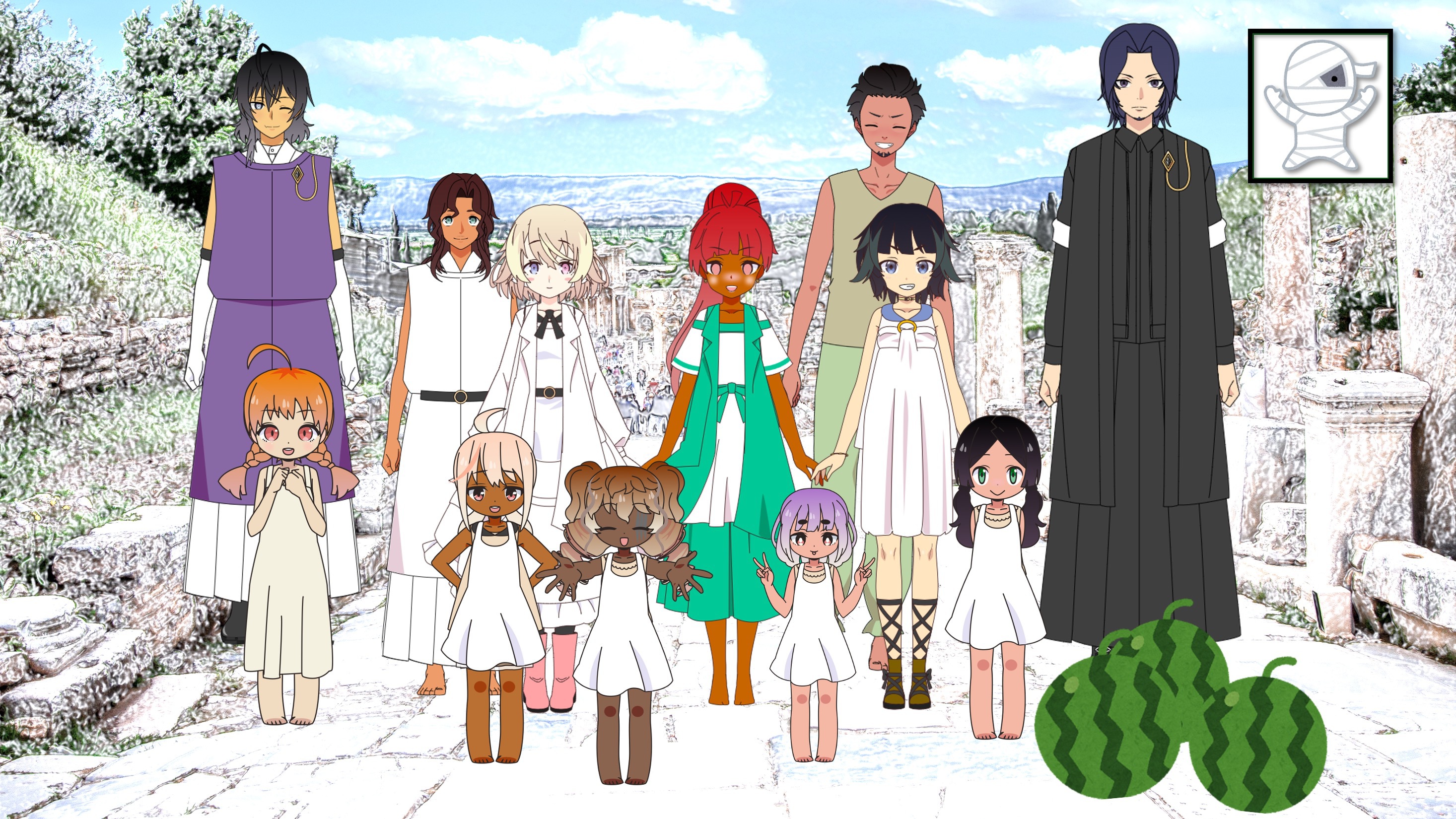
プリスカとアキラの家の教会(西暦50年代半ば、エフェソにて)
似顔絵メーカーCHARAT(キャラット)で作成
※ヘブライ人への手紙の著者に関しては諸説あり、現時点では「不明」とするのが学術的には正解です。

